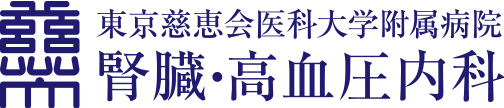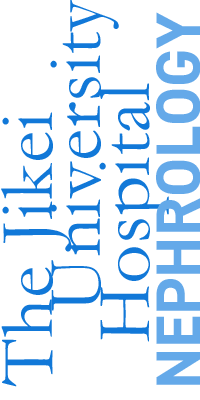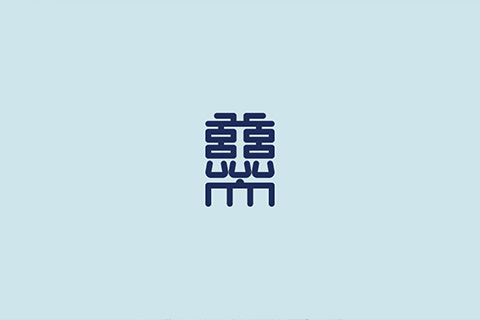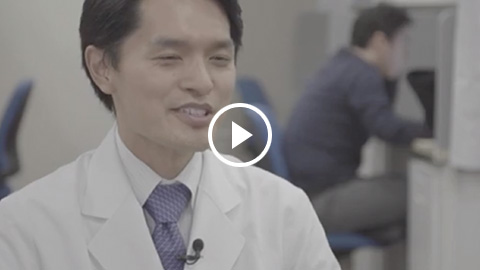再生医療に関して
当科腎臓再生チームの研究内容につきまして、以前より各種メディア等で研究に関する記事を取り上げていただいており、その後今日まで多数のお問い合わせをいただいております。現在、相談のための診療予約が入り、通常の一般診療や研究業務に支障をきたす事態を招いております。誠に申し訳ございませんが、腎臓再生に関するご質問等での診察予約は受け付けておりません。また、現時点で再生治療の被検者様募集(治験)などは一切行っておらず、治験等に関する個別のお問合せについてはご遠慮申し上げております。この点、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。尚、患者様個人からのご寄付につきましても遠慮させていただいております。腎臓再生研究につきましては、進捗があり次第、当ホームページへ掲載予定でございますので、随時ご覧くださいますようお願い申し上げます。
横尾教授から患者さんへ
横尾隆教授と共同研究をされている小林英司教授の 産学連携講座 腎臓再生医学講座 はこちらです。
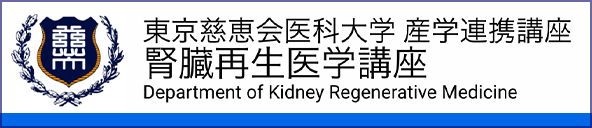
診療実績・外来担当表
診療実績
外来患者数
約2,700人/月
病 床
約50床
透析ベッド数
18床
腎生検数
約91例/年 (関連施設含め610例/年間)
当院では侵襲性の少ない超音波ガイド下の経皮的腎生検にて腎組織診断を行っています。
透析導入患者数
血液透析 約123人/年
CAPD 約21人/年
生体腎移植例
約8例/年
現在までに約150例に施行し、1年生着率は約96%で、10年生着率は約80%と非常に良好です(2020年現在)
施設紹介
慈恵医大腎臓・高血圧内科では各診療において最先端の設備を整えており、快適な優しい診療を受けていただくように努力しております。

CAPD

透析室
研究班
腎病理班
胎内での胎児間腎移植
Potter sequence(ポッターシークエンス)は腎形成不全に伴う様々な症状からなる。両側腎無形成の場合、生存の望みはない。ポッターシークエンスに対する新しい治療法として、我々は 「胎児期に異種の胎仔腎臓を移植する」というユニークなアプローチを開発した。本研究では、まず同種移植を用いてこのアプローチを検証する。緑色蛍光タンパク質発現ラット(胎生14.0-16.5日目)の膀胱付き胎仔腎臓を、子宮内の同種ラット胎仔(胎生18.0-18.5日目)に皮下移植する。出生後、移植された胎児の腎臓は尿産生能を有することが確認された。さらに長期(150日まで)の尿産生が持続した。次に異種移植で検証を行った。マウス胎仔の腎臓を子宮内のラット胎仔に移植すると、腎組織構造が成熟する。胎仔腎臓を胎仔治療のドナー臓器として用いて、子宮内胎仔への臓器移植を実証している(Commun Biol. 2025 Mar)。
胚性後腎膀胱複合組織移植による生命維持機能的腎臓置換
世界的な臓器不足に対処するためには、新しい移植可能な臓器を開発する必要がある。胚性腎組織(メタネフロス)の移植は、糸球体と尿細管の成熟を促進し、部分的な臓器機能支援を提供する。しかし、成体環境では腎臓の大きさが指数関数的に増大することはなく、このアプローチによる生命維持機能や臓器置換効果には限界がある。そこで我々は、胚性膀胱の融合と宿主尿管への多重吻合を組み合わせた新しい戦略を開発し、後腎移植と尿路統合の大幅な増加を可能にした。分割した膀胱セグメントを外科的に吻合することにより、それぞれの膀胱に4つの後腎を統合し、宿主の尿管と統合することで排泄経路を再構築した。傍大動脈領域に20個のメタネフロイを移植・統合した後、無腎臓ラットは1ヵ月以上生存し、生体内で約50,000個のネフロンを生成した。トランスクリプトーム解析から、移植された後腎の成熟度は成体腎と同等であったが、サイズが小さかったため尿濃縮能が低下していた可能性が高い。術後のサポートにより、溶質クリアランス、酸塩基平衡、電解質レベル、腎臓ホルモンレベルなどの生理的ホメオスタシスは、生命維持に必要な範囲内で正常化した。我々の知見は、胚腎組織の機能的成熟能力と用量依存的治療効果を強調するものであり、移植可能な臓器系としての可能性を示唆するものである(Kidney Int. 2025 Mar 22)。
カスパーゼ9によるアポトーシスが胎児細胞の効率的切除と疾患モデル化
胎児細胞除去モデルは、先天性疾患、臓器再生、異種移植の研究に極めて重要である。しかし従来のノックアウトモデルでは、除去の程度をコントロールすることには限界があり、条件付き除去モデルでは胎児に害を与える誘導物質が必要になることが多い。本研究では、誘導可能なカスパーゼ9システムを用いることで、内在性アポトーシス経路を通じて、マウスの胎仔ネフロン前駆細胞を正確に標的化できることを実証した。安全で胎盤透過性の誘導剤を用いたこのシステムは、特異的で迅速かつ効率的な細胞除去を容易にする。このシステムの時間制御により、疾患の重症度を正確に調整することができ、先天性腎不全から重度の慢性腎臓病まで再現性のあるモデルを作成することができる。誘導性カスパーゼ9の発現レベルが低い細胞や固形臓器の細胞はアポトーシスに弱い。しかし、この制限はX連鎖性アポトーシス阻害タンパク質を阻害することで克服することができ、このシステムの適用範囲を広げることができる。さらに、このモデルはキメラ腎臓の再生に適した発生環境を提供する。このシステムは、細胞死誘導メカニズムの理解を進め、病理学的研究ツールを強化し、腎臓病や異種移植への応用における治療開発をサポートする。(Nat Commun. 2025 Mar)。 血圧異常には体液・電解質異常が深く関わっていることから、我々は浮腫,腹水などの体液異常を高率に合併する肝細胞がんについて、発がん性物質であるDiethylnitrosamine (DEN) を用いた肝細胞がんモデルラットを作成し、どのような体液・電解質異常が起こっているか検討を行っている。
IgA腎症の臨床研究
厚労省進行性腎障害研究班のIgA腎症前向きコホート研究を主導、1000例以上の登録症例を前向きに追跡し、腎予後判定の識別・治療法選択の妥当性を検証した。また、同研究班が2012年から展開した多施設大規模後ろ向きコホートを解析し、本邦において広く行われている扁桃摘出術とステロイドの併用治療の有効性を検証、その有効性を支持する結果を報告した。IgA腎症の生検診断時の約2割に認められる腎機能低下例に対する各種治療介入の有効性についても解析を進めている。本前向き研究は一時研究を終了し、二次研究について参加多施設から公募を行い、現在進行中である。
ネフロン数研究
これまで剖検腎の解析に依存していた腎臓あたりの総ネフロン数の計測を臨床応用するため、単純CT画像検査と腎生検組織標本から総ネフロン数を臨床的に計測する新規法を独自に開発した。各種腎疾患における各種腎疾患の病態および長期腎予後との関連やネフロン数をもとに得られる単一ネフロン指標の臨床応用に向けた新たな切り口からの臨床研究を展開している。さらにAIを用いたネフロン計測により効率化と客観性を高めるべく研究を進めている。
ポドサイト数研究
ポドサイト(糸球体上皮細胞)は生理的糸球体濾過機能の中心的役割を担うとともに、その障害は慢性腎疾患の進行過程で共通に観察される病態である。ドナー生検腎と剖検腎を用いて免疫染色によりポドサイトを同定し、stereologyの手法を用いて、ポドサイト数を定量化する方法を確立した(日本医科大学・豪州Monash大学との共同研究)。ネフロン数研究と併せ、初めて腎臓あたりのポドサイト数を計測することに成功した。さらにA Iを用いた計測法を確立し効率化を図り客観性を高めることによって臨床応用に向けた研究を進めている。
ポドサイト障害の分子レベルでの解析
ポドサイト特異的に障害を誘導する遺伝子改変マウスを用いた基礎的実験を展開し、ポドサイト障害が隣接するポドサイトにも波及することや、剥離によって生じる形質転換の分子機序などの成果を報告した(東海大学との共同研究)。単離糸球体より遺伝子発現プロファイルを検討することで、幾つかの遺伝子の発現異常が早期ポドサイト障害に深く関わっていることが示された。さらに、同定された分子群について、腎生検組織の免疫組織学的検討と治療反応性マーカーとしての有用性について検討を行っている。
腎移植に関する研究
東京女子医科大学、九州大学との共同研究:Japan Academic Consortium of Kidney Transplantation (JACK)に参加し、腎移植患者を対象とする多施設共同研究を行っている。また、北海道大学、自治医科大学、当院輸血部との共同研究を実施し、ABOiでのFCTX陽性メカニズムを検証している(Front Immunol 2022)。当院単施設では、拒絶反応における血清および移植腎におけるPD-L1発現を検証中である。再発性腎炎・腎症のうち再発性IgA腎症の領域において、扁桃腺摘出術が再発を抑制すること(Front Immunol 2020)、メサンギウムC1q陽性例が多いこと(Nephron 2023)を報告し、扁桃腺と腎組織のRNA-seqをnCounterを用いてそのメカニズムを検証している。感染症領域では新型コロナウイルスやCMVについての臨床研究を展開している(Frontier Microbiol 2022, Sci Rep 2023, Clin Exp Nephrol 2025, Transplant Proc 2023)。また、移植腎における間質線維化のメカニズムを交感神経再生の観点から検証している。基礎研究では、ラット腎移植モデルにおける抗体関連型拒絶反応での内皮細胞形質変化、制御性T細胞の役割、ヒト腎近位尿細管細胞の培養細胞を用いた様々な条件下の遺伝子・蛋白発現を検証している。
インタビュー動画
スタッフ紹介
病理解析・IgA腎症チーム
腎臓発生解析チーム
腎臓再生研究チーム
腎移植チーム
腎生理・代謝班
腹膜透析に関する研究
腹膜透析を行う上で腹膜透析患者さんにとって重要なアウトカムを探索するためにアンケート調査を行ったところ、透析医にとっての重要なアウトカムとの間に乖離を認めた。腹膜透析の重大な合併症である腹膜透析関連腹膜炎の予防手段を模索している。腎代替療法研究会(EARTH研究会)の事務局として、腹膜透析・血液透析併用療法の前向き研究結果を英文誌で報告した。手術を行うことなく、腹膜透析用カテーテルから腹腔内を観察できるデバイスである腹膜透析用極細内視鏡の臨床的有用性を評価する臨床研究を行っている。また、被嚢性腹膜硬化症、重炭酸含有腹膜透析液の臨床効果、インクレメンタルPDの有用性、腹膜病理についての研究を行っている。
腎性貧血に関する研究
日本透析医学会データベースを用いた検討で、透析患者における貧血の生命予後への影響を英文誌で報告した。HIF-PH阻害薬の臨床効果について研究している。多発性嚢胞腎におけるHIF-PH阻害薬の有用性を明らかにするために、同疾患患者の血中エリスロポエチン濃度を調査している。
CKD-MBD
カルシウム、リンを始めとする骨・ミネラル代謝が腎不全、透析患者に与える影響について各種コホート研究をもとに解析を進めている。Soluble Klothoが生命予後、骨折などに与える影響および血管石灰化および体重減少に与える影響を解析する。また骨・ミネラル代謝が腎不全患者の認知機能に与える影響、認知症バイオマーカーとの関連性も解析を進めている。腎不全の進行や有病率に骨・ミネラル代謝と関連があるかレセプトベースのRWDを用いて調査を行い、早期の治療介入の手立てになる可能性を模索している。
多発性嚢胞腎(ADPKD)に関する研究
ADPKDの腎症転帰に関連する因子を、遺伝子型と併せて検証している。学内複数施設における後方視的検討と、前向きの学外多施設共同研究(レジストリ)に分かれ実施している。ADPKD主要合併症である脳動脈瘤(くも膜下出血)は、人種・地域による罹患発症率の差異が示唆されているが、国内多施設コホート研究に参加し、診療ガイドに資するエビデンス構築を目標としている。ADPKD発症に関連する細胞小器官・細胞外マトリクス蛋白に関する研究を行っている。
インタビュー動画
スタッフ紹介
腎性骨症(CKD-MBD)チーム
腹膜透析チーム
多発性嚢胞腎チーム
高血圧班
がんにおける体液・電解質異常の機序の解明
高血圧とがんには双方向性かつ多面的なかかわりがあることから、我々はこれらを包括的に検討する”Onco-Hypertension”という新規学術分野を提唱している (Hypertension. 2021)。近年、高血圧、がんいずれにおいても体液・電解質異常が高率に認められることが明らかとなっており、双方の関係には体液・電解質異常が介在している可能性がある。我々はとくにがんの中でも体液・電解質異常併発の頻度が高いとされる肝細胞がんのモデルラットを用いた検討を行った結果、肝細胞がんラットでは初期段階で体液喪失をきたしていること、おそらくこれに対する代償機序として筋におけるグルココルチコイド受容体の活性化、アルドステロンの分泌亢進、腎髄質における尿素集積などが起こる結果組織における水分、ナトリウム量の相対的増加が起こることを明らかとした(Life Sci. 2022)。肝細胞がんモデルにおける体液保持機構の活性化機序をさらに明確にするため、アルドステロンの分泌に深くかかわるアンジオテンシン受容体のノックアウトラットに対して同様に肝細胞がんを誘導し、組織における体液・電解質異常やがんの表現型に影響がでるか検討を行っている。また高血圧症や腎機能障害は大腸がん発症のリスク因子となることが報告されているが、その機序は明らかとなっていない。我々は大腸がん細胞であるRCN-9を用いて作成した転移性大腸がんモデルラット5/6腎摘により腎機能障害を誘導し、腎機能障害及びそれに伴う血圧上昇が腫瘍の表現型に影響を与えるか検討を行っている。
腎交感神経が心拍数を制御するメカニズムの解明
腎交感神経が心拍数を制御する機序や、腎臓、心臓、肝臓や筋肉の代謝に与える影響はいまだ解明されていない。我々は求心性腎交感神経除神経を行うことで、遠心性もしくは求心性のどちらが心拍数制御に関与しているか検討を行っている。また食塩感受性高血圧ラットや高血圧自然発症モデルラットに対して、腎除神経術を行って得たサンプルのメタボローム解析を行い代謝変化を検討中である。
慢性腎臓病におけるT型カルシウムチャネル抑制と交感神経との関連
我々はT型カルシウムチャネル(TCC)特異的抑制薬による腎保護作用についての報告をし(Kidney int. 2008.)、その機序として糸球体の肥大を抑制、Rho-kinase抑制を介した上皮間葉形質転換(EMT)の抑制、またそれに伴う尿細管間質の線維化の抑制が関連することを報告した。一方で、腎不全の状態では交感神経活性が亢進しているという報告がある。TCC抑制薬の中枢神経に対する作用の研究も進んでいる中、血圧に非依存的に慢性腎臓病における腎保護効果が交感神経とどう関連するかを検討中である。
インタビュー動画
スタッフ紹介
高血圧チーム