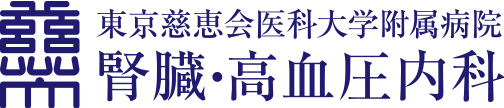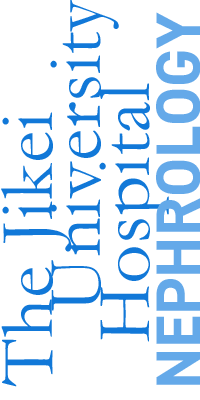2025年8月22日更新
当科、山口裕也先生、戸崎武先生、両筆頭著者による症例報告である
「Microscopic polyangiitis with histopathologic evolution in serial renal biopsies during treatment of idiopathic pulmonary fibrosis」
が、CEN Case Reportsに掲載されました。
本症例は、特発性肺線維症(IPF)治療中にMPO-ANCAが陽転化し、二度の腎生検を経て顕微鏡的多発血管炎(MPA)の診断に至った一例です。
初回腎生検では尿細管間質性腎炎のみが確認されましたが、経過中にMPO-ANCAの再上昇を認め、再腎生検で半月体形成性糸球体腎炎を捉えました。
治療はステロイド、リツキシマブ、アバコパンを併用し、腎機能の安定を得ることができました。
本症例から得られる重要な示唆は以下の三点です:
・MPAは尿細管間質性腎炎から始まり、半月体形成性糸球体腎炎へ進展する可能性があること。
・IPF自体がANCA形成のトリガーとなりうること。
・IPF治療薬であるニンテダニブがANCA産生に関与している可能性も否定できないこと。
これらを踏まえ、臨床的な教訓を二つ得ました:
・IPF患者ではANCA陽転化やMPA発症の可能性があるため、積極的なモニタリングが重要であること。
・ANCA陽性の尿細管間質性腎炎はMPAの早期像である可能性があるため、慎重な経過観察が必要であること。
ぜひご覧ください!論文はこちらです。 (Pubmedへリンクします)
本報告に関する連絡は責任著者 佐々木峻也 でお願いします。
(患者様からの個別の相談は受けかねますのであらかじめご了承ください。)